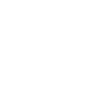住宅ローン延滞の電話が来ると、何を聞かれるのか不安になりますよね。
ですが、焦って曖昧(あいまい)に答えるより、準備して短く正確に伝えるほうが状況は好転します。
本記事では、最初の30秒で伝える要点、NG回答、自分から電話する時の台本、そして違法・過度な督促の線引きまで、やさしく解説します。
放置は信用情報や期限の利益に影響します。
いま必要な一歩を、ここから一緒に整えましょう。

住宅ローン延滞で電話が来る理由とタイミング
住宅ローンを延滞すると、早ければ数日以内に銀行から電話がかかってくることがあります。
これは、支払いの遅れを放置しないように促すためで、いきなり強い催促をされるわけではありません。
ほとんどの銀行では、延滞が1回目の段階では「確認」の意味合いが強い柔らかい連絡です。
初回の連絡は、銀行によって差がありますが、平日の午前10時〜午後5時ごろにかかってくるケースが多く見られます。
また、勤務先ではなく自宅や携帯にかけるのが原則です。
ただし、長期にわたって連絡が取れない場合には、職場に連絡が入るケースもあります。
住宅ローンの延滞から競売までの流れを詳しく知りたい方は、
→ 〖住宅ローン滞納〗1日目から競売までの全タイムライン|家と信用情報に何が起きる?
もあわせて読むと、今後の見通しが立てやすくなります。
初回連絡はいつ・誰から・どの経路?(電話/郵便の違い)
多くの銀行では、延滞が発生した当日〜3日以内に電話を入れるケースが一般的です。
連絡元は、担当支店または債権管理部署で、郵便での督促状が届く前に電話がかかる場合もあります。
これは、郵送よりも早く状況を確認するためです。
電話では、まず本人確認と延滞が事実かどうかの確認が行われます。
「支払いを忘れていた」という軽微なケースなら、この時点での対応で解決することも少なくありません。
延滞回数・経過日数で変わる“聞かれる内容”
延滞が1回のときと、3回以上続いたときとでは、銀行の聞き方が変わります。
初期は「いつ入金できるか」という日程確認が中心ですが、長期化すると「返済計画」「収入状況」「他の借入有無」など、より踏み込んだ質問がされます。
この時点で、具体的な返済スケジュールを示せると信頼性が高まり、強い催促に発展しにくくなります。
逆に「いつ払えるかわからない」と曖昧に答えると、次のステップ(文書督促・代位弁済)に進みやすくなってしまいます。
職場・家族への連絡はある?プライバシーの配慮
銀行は、原則として本人にのみ連絡します。
しかし、電話に一切応じない・折り返しがないといった状況が長く続くと、職場への連絡が入ることもあります。
この場合でも、銀行は「ローンの件」とは言わず、「◯◯銀行の△△と申します」とだけ伝えるのが通常です。
ただし、これが頻繁に行われるようなら、対応が行き過ぎている可能性もあります。
このようなケースでは、金融庁のガイドラインに照らして不当な督促でないか確認することが大切です。

電話が来たときの受け答えテンプレ(NG例つき)
銀行から電話が来たときは、まず落ち着いて状況を説明することが大切です。
焦って曖昧な答え方をしてしまうと、相手に「支払いの見込みが立たない」と判断されやすくなります。
大事なのは、「払えない」ではなく、「いつ・いくら・どのように払えるか」を伝えることです。
たとえ遅れが出ていても、事実と計画を冷静に話すことで、強い催促に発展するリスクを抑えることができます。
最初の30秒で伝えるべき3要素
電話を受けたら、最初に「本人確認→遅れた理由→支払い予定」を端的に伝えるのが効果的です。
例えば、「○月×日に入金予定です」「給与振込が遅れたためです」など、具体的な日付と理由を明示しましょう。
このとき、「なるべく早く払います」のような曖昧な答え方は避けるのがポイントです。
約束トークの作り方:金額・日付・根拠
銀行との会話では、口約束でも記録が残ります。
そのため、「いくら・いつ・どうやって払うか」という根拠を持った説明が必要です。
たとえば、「10月30日に10万円を口座に入金します。給与振込が10月29日にあります」といったように、具体的に伝えることで、相手も状況を理解しやすくなります。
やってはいけない返答:曖昧・無断スルー・虚偽
最も避けるべきは、「近いうちに払います」「なんとかします」という曖昧な返答です。
また、電話を無視することや、虚偽の説明をすることも厳禁です。
これらは銀行に「リスクが高い」と判断され、強制的な回収手続きに進む可能性が高まります。

自分から電話する場合の準備物と会話台本
銀行からの連絡を待つのではなく、自分から電話を入れることで印象が大きく変わります。
事前に必要な情報を整理しておけば、スムーズに会話を進めることができます。
準備チェックリスト:家計数値・入出金・証明書
電話前に用意しておきたいのは、
・今月の入出金予定
・給与明細または収入証明
・延滞額と支払い可能額のメモ
といった基本情報です。
これらがあると、銀行側も状況を理解しやすく、柔軟な対応が期待できます。
相談トーク台本:収入減/病気/転職直後のケース
やむを得ない事情がある場合は、素直に状況を伝えましょう。
例えば、「転職直後で給与がまだ入っていないため、◯日に支払います」「病気で一時的に支払いが遅れました」など、理由と支払い予定を一緒に伝えるのがポイントです。
曖昧な表現を避けることで、相手も納得しやすくなります。
通話記録の残し方:日時・担当・合意内容のログ化
電話でのやり取りは、あとから「言った・言わない」のトラブルになりやすいものです。
必ず「日時」「担当者名」「合意内容」をメモしておきましょう。
スマートフォンのメモアプリでも構いません。
トラブルになった場合でも、記録があると証拠として残せます。

違法・過度な督促の線引きと対処法
銀行は貸金業法の直接の適用対象ではありませんが、同等のコンプライアンス基準に基づいて行動します。
そのため、深夜や早朝の督促電話、大声での恫喝などは原則として行われません。
時間帯・言動の目安:違法/不適切の基準
金融庁のガイドラインでは、早朝や深夜の電話、執拗な催促は不適切な取立てとされています。
実際、銀行もこれに準拠する形で対応しているケースがほとんどです。
もし職場や家族に頻回に連絡が来たら
職場や家族への連絡があまりに頻繁な場合、過剰な督促とみなされることがあります。
その際は、内容をメモして、銀行のカスタマーセンターや金融ADR機関など、正式な窓口に相談しましょう。
相談窓口の使い方:記録化とエスカレーション
督促が行き過ぎていると感じた場合は、金融庁や弁護士、法テラスなどへ相談する選択肢もあります。
通話記録やメモがあれば、事実関係を明確に示せるため、有利に話を進めることができます。

延滞が続いた後に起きることと、電話で伝えるべき最終ポイント
延滞が長期化すると、銀行は「期限の利益の喪失」や「保証会社による代位弁済」など、法的な回収に進みます。
この段階になる前に、しっかりと話し合いの姿勢を見せることが非常に重要です。
期限の利益・代位弁済の前兆サイン
延滞が3か月以上続くと、督促状が届き、期限の利益を喪失する可能性があります。
これは「一括返済を求められる」ことを意味します。
その前兆として、電話の内容が「入金予定の確認」から「返済計画の再構築」に変わるケースが多く見られます。
スマホ分割・カード更新など生活への波及
住宅ローンの延滞は、スマホの分割購入やクレジットカードの更新など、他の契約にも影響します。
個人信用情報に延滞情報が記録されるためです。
銀行からの電話に適切に対応することで、延滞情報が長期化するのを防ぐことができます。
最終ポイント:現実的な返済計画と“言える根拠”
最後に大切なのは、現実的な返済計画を示すことです。
「これなら本当に払える」という根拠を持って話すと、相手の対応も変わります。
返済スケジュールを自分で把握して伝える姿勢が、信頼回復の一歩になります。
まとめ
住宅ローン 延滞 電話がかかってきたときは、最初の対応がとても重要です。
多くの場合、初回の電話は強い催促ではなく、状況を確認するための連絡です。
落ち着いて対応すれば、解決の糸口をつかむことができます。
電話の時間帯は平日日中が多く、対応の仕方によってはその後の進展にも大きく差が出ます。
特に「いつ」「いくら」「どうやって」支払うかを明確に伝えることで、相手の印象は大きく変わります。
一方、曖昧な返答や無視、虚偽の説明は最も避けたい対応です。
延滞が続けば期限の利益の喪失や代位弁済につながり、信用情報や生活全体に影響します。
電話のやり取りでは、担当者名・日時・内容をきちんとメモに残しましょう。
不当な督促と感じた場合は、金融庁のガイドラインなどを確認し、正式な相談窓口に相談することも大切です。
延滞は放置するよりも、早期の対応で解決できる可能性が高いものです。
しっかり準備をして、冷静に話すことが、今後の負担を軽くする第一歩になります。
住宅ローンや借入の不安で迷いやすいポイントを、分かりやすく整理して発信しています。焦って決めて後悔しないために、「判断の順番」と「確認先」を丁寧にまとめています。